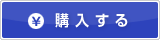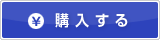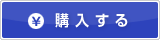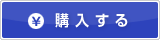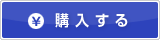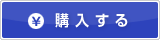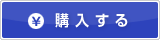「婚儀については、来月の上旬に執り行うということで進めようと思う」
新帝即位から半月ほど経ったある日、突然アスラーンの口から出た言葉にハディージェは、あやうく紅茶を吹き出しかけた。
夜風はまだ少し涼しいものの、春の盛りを迎えた中庭からはかすかに花の香りがする。
ここしばらく臥せっていたハディージェだったが、気候が暖かくなるにつれて身体も少しずつ回復してきている。とはいってもまだ完全とは言えず、今日になってようやく床上げしたばかりだ。
一方アスラーンといえば、大法官に任じられたばかりというだけでなく、新帝即位の事務処理等で多忙を極めていた。体調の悪いハディージェを見舞うため一日一度は時間を見つけて顔を出すものの、連日大法官府にこもり、めったに屋敷で就寝することもできない状況だ。
そんな彼が、屋敷に戻ってくるなり口にした言葉に、ハディージェは啞然として彼の顔を見上げた。
「その頃には、どうにかすれば一日くらい休みが取れるはずだ。施療院の休日で君の望む日取りを――」
「っ、無理……!!」
具体的な予定にまで話が進みハディージェは、ようやく我に返って声をあげる。
「……無理?」
「いえ、無理というか、その――」
とたんに眉をひそめたアスラーンに、ハディージェは慌てて言いつくろおうとする。しかし焦って言葉が出てこない。すると彼は低い声で訊ねてくる。
「なにが問題?」
(うっ――!)
切り込むような問いに、ハディージェは声をつまらせる。
医術を学ぶためにアスラーンのいるカラハリル家の屋敷にやっかいになって半年ほど経つが、こうしたときにハディージェは、彼が有能な官僚だということを思い知らされる。
彼は一度なにかを決めると、こうして障害となる項目をひとつひとつ挙げさせて、それを片っ端から処理していくのだ。
だが日常生活でそうされるとハディージェは、退路を断たれるように感じて尻込みしてしまう。
「だって、私まだ医術を学びたいし……」
「婚儀の後も続ければいいじゃないか。僕はかまわない」
「で、でも、こんなに急になんて」
来月上旬となれば、あと半月しかない。
ハディージェとしては、ようやく彼との婚約を自分の意思として受け入れたばかりだ。婚約した以上いずれ結婚することくらいわかっているが、すぐに次のことなど考えられない。
「急だって?」
しかし上擦った声で返したハディージェに、アスラーンは聞き捨てならないことを耳にしたように顔を青ざめさせた。
「……つまり君は、この期に及んでまだ僕と結婚する気にならないというわけか」
「そ、そういうわけじゃ――」
アスラーンと結婚する気がないわけではない。ただ、半月後というのが急すぎるという話だ。それをうまく説明できず、口ごもっていると彼は深く息を吐きだした。
「…………わかった」
そしてアスラーンは、長い沈黙の後そうつぶやくと、それ以上なにも言わずに踵を返した。
強く迫られなかったことにハディージェは、内心ほっとする。
しかし部屋を出ていく後ろ姿がどこか怒っているように感じられ、彼女は途方に暮れるのだった。
「ねえ、アスラーンはなんであんなに怒ったんだと思う?」
新帝が即位したばかりで忙しい日が続いているというのに、どうして彼はそんなに急いで婚儀をすすめようとするのか。
アスラーンの憤りの理由がいまいちわからないハディージェは、ドシュ海峡の島に建つ館に着くと、事情を話して訊いてみた。
「知るか!」
男性ならば彼の考えていることがわかるかもしれない。そう思ったハディージェだったが、しかし訊ねられた相手――海賊スィムルグの頭領であるハイレッティンは、彼女の問いに苛立ったように声をあげる。
なにやら海図を広げて考えこんでいた彼は、突然やって来たハディージェを追い返すことはなかった。だが彼女の質問に答えることなく、すぐに海図へと視線を戻してしまう。
「そういえばおまえ、なんでここにいるんだ?」
小さな船の模型をいくつか並べたところで、彼はふと我に返ったように顔を上げた。その言葉にハディージェも、ようやくこの館を訪ねてきた本来の用向きを思い出す。
「そうだったわ。お世話になったからお礼にと思って、これ――」
ハディージェは、手にしてきた籠にかぶせていた布を除けて、詰めてきた薬草を彼に見せた。外傷に効くものから、腹痛や頭痛などに効能のある内服薬まで、彼女が集めうるかぎりのものを持ってきたのだ。
使用法などを説明しはじめたハディージェにハイレッティンは、「そういうことじゃない」と、ため息をこぼした。
「おまえがひとりでここに来ていることを、アスラーンのやつは知っているのか?」
「話してないけど……」
アスラーンとは、昨夜あれから話をしていない。
なにせここは海賊の根城だ。ハディージェは、怖がってついてくるどころか彼女を引き留めようとする侍女のミネをなだめ、さらにはこっそりと屋敷を出てくるしかなかった。
「でも、アスラーンはここに来ることを反対しないと思うけど」
彼に聞いた話では、皇帝として即位したジハンギルはハイレッティンを海軍総提督に任命したのだという。海賊ではなく、れっきとした帝国の高官になった以上、ハイレッティンと親交を深めることにアスラーンが異を唱えるとは思えない。
しかしそう口にしたハディージェにハイレッティンは、またもや「そういうことじゃない」とつぶやき、まるで頭痛がするとでもいうように額を押さえた。
「俺は、面倒なことに巻き込まれるのは御免だぞ」
「だって、アスラーンがなにを考えているかわからないんだもの……!」
面倒と言われて、ハディージェは言い募った。
いつもならばハディージェも、男性の館へひとりで来ようなどとは考えないだろう。しかし相手がハイレッティンだと、かまわないかと思ってしまう。
アスラーンは普段から口数が少ないせいか、内心を口にせずに飲み込んでしまうことも多い。心中で思うことがあっても「わかった」の一言で片づける彼に、ハディージェは、時おり不安になってしまうのだ。
するとハイレッティンは、ため気をこぼしながら告げた。
「要はだ――」
「知るか」などと悪態をつきながらも結局は相談に乗ってくれるのが、このハイレッティンという男である。相変わらずの人の好さに、ハディージェはそう思いながら耳を傾けた。
「もう少し素直になれということだ。婚儀の時期がうんぬんということじゃなくて、相手からばかりでなく、たまには自分からも好意を示してやらないと――」
「ぶっ――」
しかし彼の話が終わらないうちに、戸口で吹き出す声が聞こえてくる。
振り返るとそこには、ハイレッティンの片腕であるジェラルが、笑みをこぼしながら立っていた。
「なんだ?」
「いや、どの口が言うのかと思って」
不機嫌な眼差しを向けたハイレッティンに、ジェラルが楽しげに言う。
「そうだよな。相手の好意に胡坐(あぐら)をかいて焦(じ)らしていたら、いつあきらめられて心変わりされても文句は言えないよな」
うん、うん、とうなずきながら続けるジェラルに、ハイレッティンは顔をしかめた。
「おまえ、何が言いたいんだ?」
「べつに? なにか思いあたることでも?」
低く訊ねたハイレッティンにもジェラルは、口の端をあげるだけだ。そして彼は、ハディージェに視線を向けると、苦笑するように悪友に言う。
「それにしてもおまえ、また懐かれたなあ」
しみじみとした口調でそうこぼしたジェラルの声は、『心変わりされても文句は言えない』という科白(せりふ)にショックを受けたハディージェの耳には入ってこなかった。
(でもわたし、べつに焦らしているつもりじゃ……)
ただ、婚儀の日程が半月後というのが早すぎると思っただけだ。
しかしハディージェにそのつもりがなくても、アスラーンには焦らされているように感じるのだろうか。
『……つまり君は、この期に及んでまだ僕と結婚する気にならないというわけか』
昨夜の彼の言葉を思い出し、ハディージェは茫然とする。
「おまえ、これから皇宮か?」
ジェラルの軽口に「放っておけ」と口にしたハイレッティンは、やがて気を取り直すように息を吐きだして訊ねた。
「そう。素直でないお前の代わりにね」
しかしまたもや揶揄され、ふたたび苦虫をかみつぶしたように顔をゆがませる。
「おまえの希望どおり帝国に帰順してやるんだから、そのくらいいいだろう」
「まあ、ジハンギル皇帝に会って遠征について話してくるくらい、かまわないけどね」
ジェラルはそう言って「俺はそこまで嫌いじゃないから」と、肩をすくめた。そして彼は、窓の外へと視線を移して太陽の位置を確認すると、いまだに放心しているハディージェに声をかけた。
「そろそろ御前会議が終わるころだね。俺は外廷に行かなければならないんだけど、一緒に来る?」
「え?」
「彼もいるはずだろ? 君から会いに行けば喜んで機嫌を直すんじゃない?」
思いがけないジェラルの申し出にハディージェは目を見開いた。
政庁である外廷は、国家の大事について話し合われるところで、遊びに行くような場所ではない。ハディージェなどが勝手に足を踏み入れていいところではない。
「いいから、いいから」
固辞したハディージェだったが、そう手を振るジェラルに、なかば強引に皇宮へと連れていかれたのだった。
*
「話があるんだけど」
夜になってハディージェがアスラーンの私室の扉を叩いたとき、彼はすでに入浴を終え部屋着に袖を通していた。
いつものように法学書を読んでいたらしい彼は、自分の部屋を訪ねてきたハディージェに驚いたように書面から顔をあげる。
視線がからみ、頭布も巻いていない彼のくつろいだ格好を目にしたハディージェは、夜更けに男性の部屋に足を踏み入れることにためらいを覚えた。
(でも、次いつ話せるかわからないし……)
新帝が即位してから大法官府に詰めているアスラーンは、みなが寝静まったころに帰ってくることもしょっちゅうで、こうして顔を合わせられる時間に帰ってくるのはまれだ。この機会を逃せば、いつまたゆっくり会えるかわからない。
「もう寝るから、明日の朝聞くよ」
しかし彼は、床に入るにはまだ時間があるはずだろうに、なぜか部屋に入ってこようとする彼女にそう言った。
「すぐ終わるから……!」
ハディージェは、慌てて声をあげた。
アスラーンのそっけない態度に、昼間ジェラルに連れられて行った皇宮で目にした光景を思い出してしまったからだ。
御前会議はすでに終わり、他の参加者たちはとっくに退出しているというのに、アスラーンは、会議が行われていたドーム下の間にいた。
そして彼の傍らには、美しい女性がいたのだ。
黒い髪にオリーブのような瞳をした女性は、驚いたことに新しく任命された国璽尚書(こくじしょうしょ)だという。
ふたりが談笑する姿にハディージェは、なぜかひどく落ち込んでしまい、そのまま帰って来てしまったのだ。いつものように無表情ながらアスラーンが、こころなしか楽しそうに見えて、話しかけることができなかったからだ。
ジェラルの話では、彼はいつも御前会議の後にドーム下の間に残り、国璽尚書とふたりだけでなにやら話しているという。
御前会議の参加者に女性、しかもあんなに凜とした美人がいるなんて、ハディージェは考えたこともなかった。浮気をしているとは思わないが、ジェラルの言うとおり心変わりされる可能性は十分にあるのだと思うと、気が気でなくなる。
「話ってなに?」
すがるような眼差しを彼に向けていることに気づかないハディージェに、アスラーンは観念したようにため息をこぼす。
「その、なんていうのかしら……」
「ああ」
表情を変えることなくアスラーンがうなずく。
(婚儀について女の方から話題にするなんて、まるで催促しているように聞こえないかしら……)
しかしどう切り出していいかわからない彼女は、とりあえず書見台を前にして絨毯に座っていた彼の隣に腰を下ろそうとした。
そのとたんアスラーンが、さっと立ち上がる。そして彼は、部屋の奥に足を向け、手にしていた法学書を壁龕(へきがん)に設けられた本棚に戻した。
(気のせいかしら)
そんな彼に違和感を覚えながらもハディージェは、話の口火を切ろうとする。
「だから、そのね――」
しかし本棚を背後に立つ彼を追いかけ近づこうとすると、彼はまた彼女から離れるようにして、今度はソファへ向かう。
さりげなさを装ってはいるが、あきらかにハディージェを避けている。そんなアスラーンの態度に、彼と話していた女性の顔が脳裏にちらつき焦ってしまう。
「明日も早いんだ。話があるならはやくしてくれないか」
いつまでもなにも話そうとしないハディージェを、せかすようにアスラーンが言う。
冷たい物言いにさらにどうしてよいかわからなくなり、その間にふたたび距離を取られそうになる。思い余ったハディージェは、逃がすまいと彼の部屋着の胸元をつかんだ。
『心変わりされても文句は言えない』
『たまには自分からも好意も示してやらないと――』
『もう少し素直になれと――』
ハイレッティンとジェラルの声がぐるぐると耳の奥でまわる。
「だから――」
気がつくとハディージェは、自らの唇をぶつけるようにして彼に重ね合わせていた。
触れ合ったのはほんの一瞬だった。すぐに身を起こしたハディージェの瞳に映ったのは、驚いたように見開いた眼差しで彼女を見つめるアスラーンの姿だった。
「っ――」
なんて大胆なことをしてしまったのだろう。
自分からこんなことをするのははじめてだ。あまりの恥ずかしさに彼の顔をまともに見ることもできない。
今日はもう、これ以上は無理だ。完全に心がくじけたハディージェは、慌てて彼の胸に触れていた手を離して上擦った声をあげた。
「や、やっぱり、わたしもう寝るわね!」
しかし立ち上がろうとしたところでハディージェは、ふいに伸びてきたアスラーンの腕に手を取られる。
そのまま引っぱられるようにしてソファに背中が埋もれたかと思うと、ふたたび唇が重ねられている。
驚きのあまりもがこうとしたハディージェだったが、角度を変えながら次第に深まる口づけに、力が抜けてなにもわからなくなっていく。
「僕は――」
なかば朦朧とした意識に浸っていると、ふいに耳元で、ぼそりとしたつぶやきが聞こえた。
「え?」
「基本的にけじめがないのは嫌いなんだ」
「……そ、そうでしょうね」
真面目で堅物のアスラーンは、そうだろう。今さらなことに、ハディージェは、うなずいた。
「なのに――」
ふいに言葉を切ったアスラーンの射抜くような眼差しに、ハディージェはどきりとする。そしてそのまま近づいてくる彼の顔から視線をそらすことも、身動きすることさえできない。
しかしその時、突然バタンと扉が開け放たれた。
「こんな時間まで仕事をせにゃならぬのは、年寄りには応えるのう」
にこにこと笑みを浮かべたアスラーンの祖父アラエッティンの姿に、ハディージェははっと我に返る。
「わ、私……、眠いからもう寝るわ。おやすみなさいっ……!」
そして乱れた襟元を搔き合わせると、彼の腕を振り払って立ち上がる。
「ハディージェ、待っ――」
背後からアスラーンの声が聞こえたが、ハディージェはかまわずに部屋から逃げ出したのだった。