  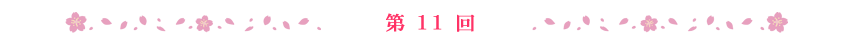
人の姿のまま、九本の尾を露(あら)わにした九尾の狐(きつね)は、そのうちの一本を撫(な)でた。青丘(あおおか)に奪われた尾だった。
「なぜ、今になって……?」 九尾の狐はふっと鼻を鳴らす。 「眠っていた『場』がね、だんだんほころびはじめたの。境を定めた結界よ。それがつい二月前に結び直された。眠っていた意識を揺さぶるには十分な影響よ」 貴女(あなた)は、あそこにあった山桜の匂いがするわね。 嬲(なぶ)るように囁(ささや)かれて、柊(ひいらぎ)は震えた。 なんということだ。衰えた山桜の代わりになる木を選定し、結界を結びなおしたことで、九尾を起こしてしまったのだ。 「目覚めたあとは、憎い男の血族の側に潜り込んだ」 「まさか、隆家(たかいえ)様が……?」 藤原(ふじわらの)隆家が、九尾と青丘の子を手にかけた人間の末裔(まつえい)。 そう言われれば、藤原氏の先祖は、百済(くだら)から渡って来た渡来人だと聞いたことがある。可能性はあった。 そこまで考えて、柊は恐ろしいことに気付く。 藤原氏は代々、多くの娘を入内(じゅだい)させてきた。その血は、帝(みかど)の御身(おんみ)にも流れている。 九尾が血を絶やしたいというなら、今、御位に即(つ)かれている今上帝(きんじょうてい)も、幼い親王(しんのう)も内親王(ないしんのう)も、皆殺してしまうということだ。 そんなことになれば、国が滅ぶ。 青ざめた柊に、九尾は一転して優しい声で話しかけた。 「本当は、国の頭からつぶしてしまいたかった。でも、守りが固くて……」 内裏(だいり)はもともと、霊的守護の強い場所だ。さらに、先の内裏での怪異から、陰陽師と僧が対策を講じたのだろう。 今となっては、良かったのか、悪かったのか。 紅桜の怪(かい)が起こらなければ警備の見直しはされなかっただろう。しかし、怪異を解決した結果、九尾の狐を目覚めさせてしまった。 「だから、隆家様に?」 隆家は賀茂(かも)家も安倍(あべ)家も嫌っていた。政敵である叔父が重用(ちょうよう)しているからと、信用していなかったのだ。 「そう。あれだけ権力があって、なぜ固い守りを敷いていないのか不思議だったけれど、好都合だった。そこに夫の匂いをつけた陰陽師が来たの」 ふと、九尾は思い出し笑いをした。 「力を削(そ)がれた意趣返しにと、夫に化けてその男を襲ったら。ほほほ! 次には夫を連れて来たわ!」 九尾はころころと鈴の鳴るような声を立てて、口元を袖で隠す。無邪気な笑い方だった。 「どうやって青丘に化けたの」 青丘は、自分の皮を被(かぶ)っているようだと気味悪がっていた。まさか、争ったという昔に剝(は)いでいたのか。 九尾は、にぃ、と唇の端を持ち上げた。 「これ」 九尾が懐(ふところ)から取り出したのは、手の平に収まる大きさの、小さな袋だった。彼女はその小袋に、愛(いと)しげに口付けた。 「青丘の毛。人間にしたら髪のようなもの。昔、手に入れたの。これを使って化けた。わたしは青丘の諱(いみな)も知っているから……そっくりだったでしょう?」 もっとも、貴女には見破られてしまったけれど。 つい、と鋭い視線を向けられて、柊は一歩、うしろに下がる。ずり、と床を擦(こす)った衣がほこりを立てた。 「この国では見鬼(けんき)と言ったわね。でも、姫。貴女はそれだけではない」 九尾が手を伸ばしてきた。逃げようとしたが、体が動かない。 九尾の細く白い指が、柊の目尻をなぞった。そのままえぐりだされそうな気がして、恐怖が背筋を走る。 「この、目。人外を視る人間は多けれど、その内側をのぞく者はそういない」 歌うように言って、九尾は柊の頰(ほお)を優しく撫でた。怯(おび)えて硬直する柊の瞳を覗(のぞ)き込み、囁く。 「私に手を貸して」 「何、を……」 困惑する柊に、九尾は優しく笑いかけた。 「貴女がいれば、どれほどの術者でも恐ろしくはない。心の奥底まで視通すその力、私に頂戴(ちょうだい)。我が子を奪われた恨み、共に晴らして」 九尾の声は甘い。母が子を慈しむような声色だ。 何も考えず、うべなってしまいたくなるような。 惑わされないように大きく頭(かぶり)を振って、きつく目を閉じる。 「嫌です!」 相手を刺激するかもしれない恐ろしさも忘れ、声を振り絞った柊に、九尾はくすりと笑った。でもね、と、駄々をこねる童(わらわ)を宥(なだ)めるように言う。 「手を貸してくれるなら、好いた男と一緒にさせてあげる」 柊は目を見開いた。心に爪をひっかけられたような、嫌な心地だ。不安を断ち切るために、あえて声を張る。 「だめ! 手を貸すことはできません。それに、貴女の手を借りることも、しません!」 彼女に、九尾に心配される筋合いはない。 だって、忠晃(ただみつ)は、柊と一緒になるために動くと決めた。決心してくれた。 「そのまま一緒になって、それで、何の問題もなく過ごせると? 貴女が一番、疑っているのに」 心の中で、一番脆(もろ)い部分に踏み込まれた。 どうして。わななく唇が、音にならない言葉をつむぐ。 「彼の枷(かせ)にならないと言える? 何の重荷にもならないと? すでに彼の可能性を一つ、潰したのに」 脳裏に、内裏で起きた赤い桜の怪が思い出された。忠晃は柊を救うため、暦得業生(れきとくごうしょう)から滑り落ちた。 さらには今回、柊との仲を許してもらうために、引き受けた隆家の件。 いつでも柊が原因で、忠晃は命を懸けて、傷を負ってきたのだ。 それが今後もないと、どうして言い切れる。 「この先も変わらない。姫、貴女の生まれ持った星の定めよ」 九尾は言い切った。 「けれど、わたしならば、その憂いを払ってやれる。これでも、仙号を持つ身だもの。人の定めを曲げるくらい、わけはない」 とても優しい声で、柊の心をえぐった張本人が誘う。目の前に、ほっそりとした白い手が差し出された。 「さあ」 魂の芯(しん)が揺れるような、ひどい眩暈(めまい)がする。救いを求めて、手を伸ばした。 この手を、取れば……。 続きは第12回更新へ! 
|