  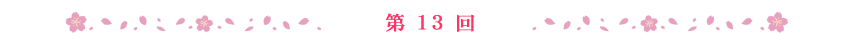
九尾の怒気が、燃えた。威圧感が肌を焼いたが、柊(ひいらぎ)は言葉を止めない。
「だって、貴方(あなた)は、一度も『仇(かたき)』とは言わなかった」 自身の恨みであって、子の無念を晴らすなどとは、一度も。 九尾とて、復讐(ふくしゅう)に意味がないことはわかっていたのだ。亡くした子が生き返るわけでもなく、その心が浮かばれるわけでもない。九尾自身の、憎悪と悲しみの捌(は)け口を求めたにすぎない。 「だからあなたは――青丘(あおおか)を殺せたのに、殺さなかった」 九尾と青丘の、身を食い合う争いを思い出す。 体格は雄の青丘が勝っていたけれど、格は金毛(きんもう)の九尾の方が上だった。なのに、尾をちぎられたのは彼女。情を捨てきれなかったのは、彼女のほう。 九尾は青丘に、どうしようもない気持ちを受け止めてほしかったのだ。 「黙れ!」 ごう、と九尾が吠えた。飛びかかろうと後ろ足を屈(かが)めた瞬間。 「――乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤、八方に陣を敷き、悪鬼魍魎(もうりょう)を縛す!」 九尾を囲む複数の声が、同じ文言を唱えた。 光の柱が昇り、甲高い声を上げて九尾がのたうつ。光の柱は八角の壁となって、九尾を閉じ込めた。 「柊殿は無事か、忠晃(ただみつ)!」 柊たちの後方から走ってきたのは、忠晃の父、青丘の主(あるじ)である賀茂光栄(かものみつよし)だった。 彼の他にも、陰陽頭(おんみょうのかみ)である安倍吉昌(あべのよしまさ)を先頭とした陰陽師たちが、八方から駆けつけた。 十人近い人数で九尾を囲い、縛ったのだ。おそらく、忠晃の策はこれだろう。 複数の力を必要とすることからもわかる、とても難しく、強固な縛術。術を施した彼らは、地に伏せる九尾にじりじりと近付き、様子をうかがっている。 これでもう大丈夫。柊が力を抜きかけた、その時。 薄氷が砕けるような音がした。 「おのれ、小賢(こざか)しい!」 九つの尾を振り乱した九尾が、縛りを払ったのだ。しなる尾に破壊され、光の壁が霧散する。 「まさか、八方陣を……!?」 光栄が声を上げた。焦る陰陽師たちを睥睨(へいげい)し、九尾が咆哮(ほうこう)する。 「愚か者ども。仙術を修めたわたしに、人ごときが勝てるものか!」 忠晃が、すぐ側(そば)で息をついた。もう、どうしようもないような、ため息だった。 陰陽師たちが力を合わせた術が通じない。 どうしよう。打つ手が、もう――。 「おいおい、はしゃぎ過ぎだろ」 のんびりと間延びして聞こえたのは、青丘の声だ。あまりに場違いな言葉に、驚いて振り返る。九尾に呪縛されたはずの青丘が、狐の姿で歩いてくる。 「動けるの……?」 「おまえに内心を言い当てられて、あいつが揺れた。それに、光栄が来たからな」 柊と忠晃の側を通り過ぎる時、いつものような、気安い調子で言う。 「隙(すき)は俺が作る。滅してくれ」 「まっ……」 待て、と、声をかけようとしたのは、柊か、それとも忠晃だったろうか。 何か固く決意したような感じがして、それが恐ろしかった。 柊が言い切る間もなく駆け出した青丘は、陰陽師に飛びかかろうとした九尾の横腹に体をぶつけ、尾を尾でからめとりながら、九尾の動きを封じた。 「この程度で!」 吠えた九尾だが、しだいに声が細まる。青丘の体が、先端から石に変わっているのだ。そのせいで、青丘に押さえられた九尾の体まで石化が始まる。 「青丘……?」 まだかろうじて動く首をまわし、青丘がこちらを見た。労(いた)わるように、目を細められる。 流れ込む、青丘の感情。 それは、九尾を道連れに、自滅する意思だった。 青丘は、もう、九尾を止めるにはこれしかないと思っている。自分の命を使う以外に、方法がないと。 九尾の心には、青丘の言葉を聞く隙間がない。その余裕は、遠い昔になくした。 説得できず、かといって、陰陽師たちの力を束ねた術も通用しない。ならば、青丘がその命を引きかえにするしかない。九尾には、九尾を。 ――こいつは連れて行く。俺ともども、後の始末を頼む。 なに、それ。 湧いたのは怒りだった。何を勝手に、と問い質(ただ)すこともできないまま、青丘は妻である九尾を巻き込み、ひとつの岩へと姿を変えた。 陰陽師たちが、好機とばかりに封をほどこす。忠晃は封印に力を貸す余力がないのか、青丘が九尾と共に封じられた衝撃からか、目元をおさえたまま動かなかった。 柊は、いま起こったことが夢のような、夢であればいいと思うような心地で、呆然(ぼうぜん)と見ているだけ。 「このままでは、いつ復活するやもしれませぬ。封殺いたしましょう」 陰陽師の一人が、陰陽頭に進言した。 「……封殺?」 呆(ほう)けたまま、聞こえた言葉を繰り返す柊に、光栄が答えた。 「封印を施したまま、魂を抜き、存在を消滅させる。九尾を退治するには、もはやこの機に封殺するより他ない」 「それは……」 そんな終わりは悲しい、と思って視線を落とし、はっと顔を上げる。 「青丘は……?」 九尾と、妻と一緒に石になった青丘はどうなるのか。 「青丘も共に滅さねばなりません。あれは己(おのれ)を礎に、九尾を石に押さえ込んだ。切り離せるものではない。……青丘も、己だけが助かることは望まぬ」 「そんなっ」 唇が震える。青丘の主である光栄から、そんな言葉が出るとは思わなかった。 陰陽師たちは、異論なし、といわんばかりに沈黙している。 忠晃も、何も言わない。 「待って、待ってください! そん、そんな、本当に、他に方法はないのですか!?」 柊は声を荒らげた。たしかに、青丘は滅してくれと言った。言ったけれど、このまま青丘と九尾を消すのは嫌だ。 だって、青丘には小さな頃から世話になった。何度も、忠晃と一緒に助けてくれた。 幼い頃の、認識する世界が狭く、両親にいとわれていると思いこんでいた柊にとって、気軽に遊び相手になってくれる青丘の存在が、どれだけありがたかったか。 九尾だって、殺されかけたけれど、彼女の内面をのぞいた以上、このまま死んでいいなんて思えなかった。 大切な子を亡くした九尾の悲哀は、及ばずとも理解できる。なにより、彼女が抱えていた寂しさは、共感できるものだった。好きな相手に、そばにいてと言えない、あの凝り固まった心も。 彼女は、青丘と話をすべきだった。どんなに泣いても、怒っても。言葉を尽くした結果が、また拒絶しかないのだとしても。 簡単に殺して終わりになど、したくない。 青丘が何百年もかけて探した妻との再会が、こんな終わり方でいいはずがない。 青丘がよくても、納得していても、柊が承知できない。 「忠晃様! 光栄様!」 半ば泣き叫ぶ態(てい)で詰め寄る。柊よりも、もっと、この事態を受け入れられないのは、彼らのはずだ。 「……そうですね」 億劫(おっくう)そうに陰陽師の面々を見渡した忠晃は、最後に陰陽頭を見すえた。 「ただ封殺しただけでは、祟(たた)りがないとも限りません」 「だが、このままにはしておけんぞ。どうする気だ?」 陰陽頭の声は厳しい。たかだか式神への情で、国への脅威を野放しにする気か。そんな叱責が飛んできそうだった。 忠晃は一度、深く息を吐いた。 「この封印を――私が守ります。子子孫孫に引き継がせても」 続きは第14回更新へ! 
|