  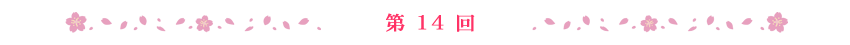
陰陽師たちは、黙りこんだ。陰陽頭(おんみょうのかみ)も、光栄(みつよし)でさえ、絶句した。
忠晃(ただみつ)の言葉をきちんと理解できない柊(ひいらぎ)だけが、祈るように袖(そで)の下で手を握る。 「よいのか、忠晃。天地の霊気を取り込んで、いずれ九尾(きゅうび)は復活する。その時、真っ先に引き裂かれるのは、おまえか、おまえの子や孫だ」 陰陽師の中でも、年嵩(としかさ)の男が、戸惑うように訊(き)いた。先達の者が若者をたしなめるような、忠晃を案じる気遣いに満ちている。忠晃の申し出は、それだけ忠晃にとって負うものが大きいのだ。 「祀(まつ)り上げてなお、恨みが薄れずよみがえるなら、その始末も必ず」 忠晃は引かない。彼は怒っていた。たぶん、青丘(あおおか)に対して。言ってやりたいことが、山ほどあるのだろう。 「……おまえの気持ちは、わからんでもない。だが、九尾はともかく、光栄の式神が、目覚める保証はないぞ。封の、術の起点だ。それでも?」 陰陽頭が、柔らかい声で質(ただ)した。目覚めぬかもしれん者を、その亡骸(なきがら)に等しい石の側で、待ち続けるのかと。その無情さに、耐えられるのかと。 柊は、喉(のど)に空気が詰まったように呼吸があいまいになる。 「……承知しております。それでも、この封を守ります」 忠晃が、吐息に乗せて言った。重い、宣言だった。 場が、再び沈黙する。くだらないと一蹴(いっしゅう)することは、誰もしない。忠晃の本気も、誠意も認めているのだ。ただ、それだけではまだ足りず、忠晃の提案を是とうなずけない。そんな迷いが感じられた。 「――方々。我が賀茂(かも)の家が、封印の責を負うと誓いましょう。どうか、お許しいただけぬか」 助け船を出したのは光栄だった。忠晃個人だけでは、九尾という大きな災いの封印を託すには足りなかったのだ。光栄はそこに、賀茂という一族を懸(か)けた。 「……よかろう」 柊が握った手の感覚が失(う)せるくらいの時間を要して、陰陽頭がうなずいた。そこここで、安堵(あんど)とも嘆息ともつかない息がもれる。 きっと、柊には想像もつかないほど、大変なことなのだろう。 でも、話の決着はついた。ひとまず、青丘と九尾が消されることはない。 安堵で、柊の膝(ひざ)から力が抜ける。 「柊殿!」 緊張の糸が切れたのだ。一瞬にして、柊の意識は(やみ)闇に沈んだ。 暗い中、浮かんでは消えるいくつもの光景。 ある時、それらが晴れて、柊は賀茂家の簀子(すのこ)に腰を下ろしていた。 「失敗したんだ、俺は」 気安いくせに、苦い声を出すのは、隣に座っていた青丘だ。 「子を亡くして、復讐(ふくしゅう)しようとするあいつを止めて、傷付けた。俺がそばにいるだけで傷口を広げると思った。だから離れたんだが」 淡い色の髪に、外(と)つ国の衣装を着た男の姿は、つい最近見た気もするし、遠い昔の記憶のような気もする。 「一番失敗しちゃならんところで、やらかした。俺は、どんなに拒絶されても、あいつのそばを離れちゃならなかった。惚(ほ)れて、口説いて、連れ出したのは俺だったんだから」 これは、青丘であって青丘ではない。彼は今、石となって、妻である九尾と共に在る。 ここにいるのは、柊に流れこんだ彼の感情だ。 柊は夢を通じて、青丘の感情を整理しているのだ。 「まあ、俺があいつのそばにいていいのかと、自問する時間が長かったせいで、余計に孤独にさせたが……その間に俺が思い知ったのはな、柊。あいつがどう思うかは関係なく、俺があいつのそばから離れたくないってことだった」 じっと庭を見つめていた青丘が、はじめて柊を見た。穏やかな顔だった。 九尾も、離れて欲しくなかったの。拒絶した手前、自分勝手な言い分だとわかっていたから、口にできなかっただけで。 柊の言葉は、青丘には伝わらない。これは彼からの一方通行だ。 「だから、柊。おまえは間違うなよ」 わかっている。柊はうなずく。 柊も、忠晃と離れていられない。結局は、彼のことを考えて身を引くとか、そんなにできた人間ではなかった。 だから、どんなに彼のお荷物になっても、一緒にいられるように頑張る。 すれ違っても、簡単にあきらめなどしない。 もう何も、こちらからは伝えられない青丘に、それでも大丈夫だとうなずいた。  柊が目覚めると、九尾の封印から五日が経(た)っていた。
柊が目覚めると、九尾の封印から五日が経(た)っていた。目覚めた、と言っても、床から起き上がれる状態ではない。九尾の内側をのぞいたせいで、体も精神も疲弊しきっており、浅い微睡(まどろ)みから抜け出せないのだ。 以前のように、視力を失うことこそなかったものの、痛手は大きい。 何日も何日も、眠っては目覚めた。 夢現(ゆめうつつ)の中で、何度も青丘と金色の九尾の姿を見た。彼らの姿が浮かんでは消え、何が現実なのか曖昧なまま横になっていると、にわかに周囲が騒がしくなった。 何だろうと思って、重いまぶたをゆっくり押し上げる。 「柊殿」 耳に馴染(なじ)んだ声が聞こえて、驚いた。 忠晃だった。狩衣(かりぎぬ)姿で、綺麗(きれい)に背筋を伸ばして、柊のすぐそばに座っている。 一瞬、賀茂家にいるかのような錯覚に陥る。だって、父の屋敷では、こんな風に気軽に顔を合わせることができなかった。 「お加減のほうは……あまりよろしくないようですね」 訊いておきながら、柊の様子を見て、勝手に判断したようだ。大丈夫です、と返しながら、上半身を起こす。体の節々が悲鳴を上げたが、無視できる程度の痛みだ。 向かい合って忠晃を見つめる。 忠晃は無表情だった。いつもの無愛想な顔と、同じようで、違う。 「忠晃様こそ、お怪我(けが)のほうは……?」 柊よりも、忠晃のほうがぼろぼろだったはずだ。けれど忠晃は、特に何も言わず、首を横に振った。大事はない、ということだろうか。 いつも歯に衣(きぬ)着せぬ物言いをする彼が言葉少ななことに、不安になる。柊まで黙り込んでしまって、部屋が静まり返った。 「柊殿」 どれだけ時間が経ったのか。ぽつり、と忠晃に呼びかけられた。柊は、はい、と返事をしたが、かすれて音にならなかった。忠晃は、かまわず続けた。 「私は今回の一件で、下野国(しもつけのくに)に荘園(しょうえん)を賜(たまわ)りました。――が、それは表向き。真実は、都から離れた下野国にて、九尾の封印石を守るためです。陰陽寮の上役や、道長(みちなが)様、隆家(たかいえ)様とも協議の上、決まりました」 頭はまだぼんやりしているが、なんとなくわかる。もし、忠晃の力が及ばず、九尾が復活し止められなかった場合を考えて、できるだけ都から遠い場所を封印の場に選んだのだ。 「石を運ぶのに同行しなければならないので、これから少しの間、都を離れます。すぐに戻りますが、お知らせしておこうと思いまして」 淡々と告げる忠晃に相槌(あいづち)を打ちながら、そうか、そうなったのか、と思った。 まだ夢現で、実感がなかったのだけれど。どんなに忠晃のうしろを探しても、あの淡い色の髪も、外つ国の衣装も、視(み)えない。 「もう、青丘は、いないのですね」 柊がこぼした次の瞬間、取り繕っていた忠晃の表情が崩れた。返事をしようとしたのか、それとも他のことを言おうとしたのか、忠晃は唇を開いたが、彼から洩(も)れたのは押し殺した嗚咽(おえつ)だった。 柊も、自分の言葉に打ちのめされて、涙があふれる。胸の一部がえぐられたような喪失感が、つらくてたまらない。 寂しくてどうしようもなくて、伸ばされた忠晃の腕を、すがるように受け入れた。 抱きしめられ、忠晃の胸に顔を押しつけて泣く。目元に熱がたまって、喉が焼けた。 忠晃も泣いている。柊の肩に顔を埋(うず)めて、震えながら泣いている。 青丘を失うと思ったことはなかったのだ。一度も、想像すらしたことがない。 青丘は以前、「たぶん、次の主(あるじ)は忠晃だ」と言ったことがある。今の主である光栄を看取(みと)ったら、忠晃の最期まで付き合うはずだったのだ。 あの、陽気で気安い声がないだけで、世界から太陽が消えたような気がする。 「……あのっ、馬鹿が……っ! 勝手に……!」 嗚咽交じりの暴言は、切れ味がなく、言葉にすらなっていない。 言いたいことが山ほどあるのに、相手にはもう伝わらない。そんな思いを必死に内に閉じ込めようとしているのが、柊には見えた。 それきり、お互い交わす言葉はなく、抱き合ったまま泣き続けた。 続きは第15回更新へ! 
|