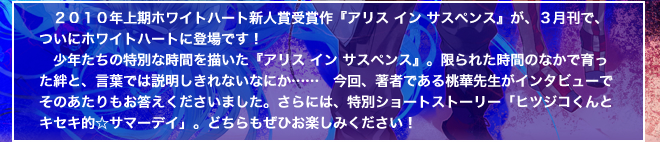夏っていいよな。テンションは一年のなかで絶頂に跳ねあがり、グルーヴが街に溢れかえる。女の子も薄着になってくれるし、とにかく、開放的じゃないか。路上でいきなり吠えても、違和感のない季節。
実際は暑さにうんざりして秋になれと願ったりしてるけどね。それはどの季節も同じだろう。秋には冬のイベントが待ち遠しいし、冬は寒くて春に思いを馳せて、春には強くなる太陽に夏を待ち望む。でも、過ぎたらさみしくなるのは、夏だけって気がする。あれほど涼しくなれと念じていたのに、いざ秋になれば物足りなくなる。心に残るのは、ぽかんとした喪失感。これってほかの季節にはない恋しさ。
だけど、夏を好むのはおれたちだけじゃない。トラブルってやつも、夏が大好き。頭まで沸騰したガキたちは、開放的なテンションに後押しされて、暴力沙汰の嵐を起こす。トラブルは日差しの中できらめきながら、理性をゆっくりゆっくり溶かしていく。夏のストリートはちょっとしたリング。袖の振りあいでさえ、戦いのゴングに変えてしまう。そう考えると、夏ってアルコールみたい。気を大きくさせて、人を通常だったらやりもしない行動に走らせる。
でも悪いことばかりじゃない。バカなことも「ひと夏のあやまち」ってことで目をつむってくれるのは、夏だけじゃないか。

おれは街を漂いながら音楽を聴いていた。遠い昔に活躍していた、ニュー・メタルバンド。七弦ギターの歪んだ音色と、打楽器に近いベースのリズム。悲痛なボイスはどんどん泣き声に近づいていく。耳から脳内に絡まっていくダークな世界観と不協和音。なんでこんな暗い曲を好んで聴いているのだろう。自分で自分がなぞ。だけど、激しい音楽とシャウトを取りこむと、たまらない気分になる。体のなかが空洞になって、すべてから解き放たれていくみたい。不快なのに爽快。治安の悪いこの街にぴったりなところがいいのかもしれない。
西の空には夕日が落ちかかっている。空のカラーはきれいなガランス。うっすらと広がる雲が西に進んでいく。おれが空から地上へ視線を落とすと、歩道が夜の準備で明かりを灯しはじめていた。アスファルトには街へ向かう人と影。これからが一日のスタートだといいたげなムード。路上で繰り広げられるのは、一夜かぎりのボーイミーツガール。
歩いていたら、うしろから頬をはさまれた。
「だーれだ? だーれだ?」
爆音の間にかすかに届く、女の声。そのまま顔をサンドした状態でぐいっと引っ張られる。ヘッドホンがはずれて、肩にぽすんとぶつかる。うしろに仰け反ると、明るい笑顔がのぞいていた。
「アリス」
呼びかけると、アリスは華やかな声をあげて、ぱっと手を離す。アリスはおれの友達。夏のはじめに出会った最近のつるみメンバーのひとり。遠い田舎から引っ越してきて、それからいろいろあったけど、このころは仲良くやっていた。アリスはおれらといるのがいちばんたのしいという。友達冥利(みょうり)につきる台詞。
「わー、うれしい。アリスのこと、すぐわかっちゃうのね。ウケる」
どこがウケるのかわからない。顔を見せられてわからないはずがないだろう。簡単すぎるクイズでも、おれは難問をといたようにえらぶってみせる。だって女って、ノリをあわせないと、すぐにむくれるじゃないか。
「こんなところでなにしてるのかな?」
「散歩と音楽鑑賞」
おれはヘッドホンをアリスにかぶせる。アリスはニュー・メタルなんて聴かないようだ。どうでもよさそうに髪の毛をくるくると指に巻きつけている。シブいやクールなんて感想はなし。趣味は強制できないものだけど、興味ない態度すぎて、ちょっと傷つく。
「音楽プレーヤーとか高くない? よく買えたね。あ、音楽が好きだからお小遣いためたのか。えらいのね」
アリスはヘッドホンをはずしながら、イノセントな表情を浮かべる。まさかパクッたなんていえなかった。おれは肩をすくめる。アリスはそんなおれの対応に首をかしげるだけでなにもいわない。どうしたのかしら。そんなところ。
今日のアリスは派手なパレオを巻きつけただけの南国スタイル。足元はごついグラディエーター。来年まで生き残れそうもない、今年だけのトレンド。手首を防御するみたいにいくつもはめられた細い腕輪が、しゃらしゃらととがった音をたてる。これから遊びますって気合いのあらわれ。いますぐデートにだって挑めそう。
誰かと約束をしているのだろうか。そう質問すると、アリスは首を横に振った。
「んーん。誰とも遊ばないよ、あ、でもいっしょに遊ぶよ。あは、どっちだよみたいな、マジウケる」
なにがいいたいのかわからない。ひたいをもみこんでいると、アリスはぴしっとおれに向かって指をさしてきた。
「今日は、ヒツジコくんと遊ぼうと思っていたのです」
どうやら、おれが目的だったようだ。おれが自分を指さすと、アリスは何度も何度もうなずいた。
「さがしたんだよ、家にいないし、ヒツジコくんって携帯電話持ってないしね。って、アリスも携帯電話ないけど、ウケるし、いまどき持ってないとかひどくない? でも三十分で見つけちゃった。アリス、すごくない? これって運命的じゃない、ほーめーてー」
アリスはテンション高く、手足をばたつかせる。これは頭をなでるまでとまらない。いつまでもガキみたいなやつ。女って、男よりも精神年齢が高くなかったか?

それからおれとアリスはふたりで街を歩いた。見ているだけでつま先が痛くなりそうなほど高いヒールをはいているのに、アリスはすいすいと進んでいく。ヒールは目測十センチ。アリスの足の裏はどうやって体重を支えているのだろう。おかげでチビなおれはアリスを見あげる形になる。ヒール文化は低身長男子へのいやがらせだ。
夜になっても、太陽の残り香は街中に充満している。焼けたコンクリートの匂い、湿気をふくんだぬるい風。街のどこへいっても、カーニバルみたいにはずんだ声がする。フィーバーした空気はこれからがのぼり坂。慣れた景色でも、アリスは初めてみたいに駆けていく。散歩にいくイヌのほうがまだおとなしいってくらいのハイテンション。アリスはちょこまか動きながら、おれに語りかける。アリスといると退屈しない。どんなものでも新鮮に感じる。沈黙をおそれるような質問のラッシュだって、面倒じゃなかった。ねえ、たのしいね。ヒツジコくんはたのしいかな。アリス、おもしろいよ。ヒツジコくんはどうなのかな。
パレオのハイビスカスの柄がひらひら揺れている。このまま花火みたいにはじけてしまいそう。アリスの瞳が大きく見えるのはメイクのせいだけじゃないだろう。
「ヒツジコくん、もっともっとたのしいことしようよ。いっしょに、うれしいことしよう」
結局は、金もないガキふたりが街を歩いていただけ。なのに、おかしなことに思えた。アリスが駆けるヒールの音はまるでタンバリンを鳴らしているよう。
アリスはしあわせそうだった。どうしてかと質問すると、なんでもないことのようにアリスは答えた。
「いっぱい、いっぱい、思いっきりでいたいの。だって、食べないとお腹がすいちゃうでしょ」
おれはなにかを返そうとして、どんな言葉をいえばいいのかこまってしまった。アリスはくちびるをとがらせて、それから恥ずかしそうに髪をなでる。
「意味ぷーって顔してる、ひどくない? マジウケるし」
おれは両手をあげて、おどけた仕草で軽い謝罪をする。アリスは声をはじけさせ、まぶしそうに空をあおいだ。
「じゃあね、いつか、教えてあげるね。アリスがなにをいいたいか、教えてあげる。そのときは、そんな顔をしないで、マジで聞いてね」
期待していると、おれはいった。アリスは両手を広げてくるくる回る。なんか知らないけど、へんなやつ。

はしゃぎまわる女はガキと同じ。目を離したら、ふいっと消えてしまう。そばについて歩いていたアリスはいつの間にかいなくなっていた。おれはため息をついて、きた道を戻る。しかたないやつ。あきれているのか、笑っているのか、どっちなんだろう。
アリスはすぐに見つかった。クレープ屋をまえに、真剣な表情でメニューをのぞいてる。戦に向かう侍のほうがまだ気楽なもんだろうってくらいの気迫。
おれはアリスに呼びかけようとして、手を振りあげた。それがいけなかった。
なんか、指にささった感触がした。
続いて指先になまなましい体温が伝わる。おそるおそる視線をあげて、つい、頬が痙攣(けいれん)した。苦笑が口からこぼれでる。おれの指は、ちょっとつっぱった感じの兄ちゃんの鼻の穴に突きささっていた。奇跡的な鼻フック。どうしてこうなった。説明してくれ、ジーザス。
そのままビル陰に連れこまれる。気づいたときには、背中が壁に接触していた。鼻フックにつめ寄られると、おれはすっぽりそいつの影におおわれてしまう。鼻フックがおれの胸ぐらを引っ張って、なにかを叫んでいた。下品な声。鼻フックの目には赤い線が走っている。薬をキメたにおいも、アルコールの気配もないから、ただの夏の破壊衝動に冒されたのだろう。導火線が短すぎる。
普段だったら、おれは平謝りをしていたと思う。ここまで怒ることないとは思うけど、やっぱり悪いのはおれだから。夏のせいかもしれない。男の血走った瞳に感化されたのかもしれない。鼻フックの拳が頬に打ちこまれる。痛みよりも先に衝撃がきて、口のなかが切れた。おれはどうして、そんなことをしてしまったのだろう。
おれはすぐさま頭突きをいれた。こんなやつにかまってて、アリスとはぐれたらどうするのだ。鼻フックの手が離れると、防御の姿勢をとる。上目遣いで鼻フックを挑発する。おれは街中に響かせるみたいに吠えて、鼻フックの鼻をねらって突っこんでいった。

結果、三分。余裕の勝利。おれだってやるときはやる。服の汚れをはらって、ビルの陰から顔をだした。アリスが道端で眉をさげてきょろきょろしている。平和な光景が、ひどく鮮明に見えた。アリスの両手にはクレープ。おれを発見すると、泣きそうな顔から笑顔に戻る。
「ヒツジコくん。どこにいってたのよ」
アリスは心配そうにおれにクレープを差しだした。それから、おれの頬に気づいた。
「ヒツジコくん、どうしたの?」
なんでもないと伝えた。そう、なんでもない。ただのちょっとした喧嘩。どっちが悪いなんて、もうどうでもいいことだろう。おれはクレープの礼をいって、ひとくち食べた。血の味がする。まずくはないけど、違和感がある。
おれは気持ちをクレープで冷まして、アリスに笑いかける。
だが、フードを引っ張られた。振り返るまえに、背中に一発いれられる。そのまま前のめりに倒れて、クレープを落としてしまった。
おれを殴ったのは、リーゼントのいかつい男。アロハのシャツからのぞく胸は、漫画みたいに分厚い。アリスの悲鳴が聞こえる。リーゼントのうしろには、五人組がひかえている。そのなかに、さっきの鼻フックがいた。ドレッドの男にささえられ、おれを指さして、なにかうめいている。
「おい、てめェ。おれの連れが世話になったんだってな」
今度はリーゼントに胸ぐらをつかまれて、引き起こされる。あせった。さすがにおれもこの人数じゃ完敗。負けるのはいい。だけど、それはおれだけのときだ。おれは買った喧嘩に後悔をした。おれだけならともかく、アリスがいる。
「す、すみませんでした……」
謝るしかなかった。おれは殴られてもかまわないが、アリスには関係ないのだ。でもやつらは許してくれない。
「おい、こんな腰抜けよりも、おれらと遊ぼうぜ」
そうドレッドがアリスの肩に手を置こうとする。おれはリーゼントの手を振りはらって、アリスのまえに立ちはだかった。

それで、なにをしたって? 決まってる、土下座をするしかないじゃないか。
ひたすら謝る。アリスは関係ない、けじめはおれだけでいいと主張する。一発、こめかみに思い切りいれられた。また地面に転げて、頬にクレープがすれる。アリスが駆け寄って、おれのそばでしゃがみこんだ。地面に手をついたので、アリスまで謝るのかと思った。でも、アリスって、そんな女じゃなかったんだ。
アリスは素早くグラディエーターのチャックを下ろすと、迷わず両足とも脱いで、クレープといっしょにやつらに投げつけた。一瞬、やつらがひるむ。アリスが攻撃するとは思わなかったようだ。おれの腕をとると、アリスは裸足のまま駆けだす。
「ヒツジコくん、逃げないと」
おれも走りだす。アリスに、こそっと耳打ちをした。分かれて逃げて、今日出会った場所で落ち合おう。背後からやつらが追ってくる気配がする。おれはアリスが遠ざかっていくのを見送りながら、足をとめた。アリスはおれが逃げていないことに気づかない。街の喧騒のなかにまぎれていく。
後頭部にがつんとぶちこまれたのは、すぐだった。

結果、袋叩き。ボロ雑巾のほうが、おれよりまだきれいだろうってくらい。体中が痛むけれど、ひどいのは見た目だけだろう。骨がイカれている様子はない。どのくらいの時間が経過したのか。鼻血を出して、歩道に転がっているおれのもとにアリスが戻ってきたのは、やつらがいなくなって、しばらく過ぎてから。アリスが座りこんだ。こんなときでも足の間に注目した自分がいやになる。アリスは足を汚して走ったというのに。
「大丈夫?」
おれはうなずいた。なんて一日だ。視界に入るのは、人々の足と靴。アスファルトに添い寝されていると、にぎやかさも遠く聞こえる。誰かが跳ねて、砂利がおれにぶつかった。
なにもいわないおれに、アリスは泣きそうな顔になりながらハンカチを差しだしてくれた。やわらかく血をぬぐう。ごめんねと、アリスは繰り返した。逃げ遅れたのはおれだと伝えても、アリスは謝りつづける。ハンカチに、真っ赤な血がしみこんだ。
「ありがとう、ヒツジコくん」
アリスはそういった。おれはゆっくりとアリスに目を向ける。
「ヒツジコくん、ほんとは逃げなかったんでしょ、アリスがいたからよね」
おれは笑ってしまう。そもそも、おれがいけない。バカな喧嘩をして、負けそうになって、アリスを危険な目にあわせそうになって、土下座をして、アリスを守れもしなかった。こんな、どうしようもない男がほかにいるのだろうか。むしろ、責めて罵ってくれたほうがいい。カッコ悪いにもほどがある。おれはそう説明した。こんな状態でやさしくなんかされたくなかった。
でも、アリスは引いてくれなかった。
「いいの。あいつらに、仲間がいるとか想像つくわけないじゃん。っていうか、謝ったんだし、もっとやってくるほうがひどくない?」
おれは今、誰よりもダサい。これは弁解しようがない。アリスは一言もおれを責めなかった。あんまりにも必死なので、ありがとうございますとだけいった。卑屈なおれの態度にも、アリスは何回も首を振る。
「違うもん、王子さまみたいだったもん、カッコよかったよ」
「王子さま?」
「そうなの。あのね、ヒツジコくんの喧嘩のせいとか、どうでもいいんだよ」
ふふっと笑って、アリスは落ちているグラディエーターをひろう。両手にもって、なにかメダルみたいにかかげた。
「ただね、ヒツジコくん、アリスのために土下座して、そいで、逃げなかったの。それがいいの。カッコいいの。そういうの、女の子は王子さまって思っちゃうのよ」
アリスは裸足のままでいる。おれは立ちあがると、背伸びをして、アリスのひたいにキスをした。やさしい女友達への感謝の気持ち。アリスの目が、まん丸になる。おれは前髪に息を吹きつけるように笑った。汗ばんだ手のひらと、ざわざわとした喧騒。ずっとずっと先で、車のライトが流星みたいに流れていく。ビルが空をでたらめに切り取りながら、強風を送りこんできた。アリスのハンカチが飛ばされて、雑踏に姿を消してしまう。
ここまでいってくれるんだから、いじけているわけにはいかない。おれはアリスの背中に手を回すと、そのままかかえあげた。いわゆる、お姫さまだっこ。殴られた腕に痛みが走るけど、涼しい顔を作ってみせる。こんなに情けないおれでもアリスは王子さまといってくれる。正直、泣きたいほど痛かった。本音は、かなり重かった。だけど、おれは笑って地面を踏みしめる。
裸足のプリンセスのために、このくらいはカッコつけるべきだろう。