



給湯室で、コーヒーを手にして和孝(かずたか)は情報交換に勤(いそ)しんでいた。
「去年オープンしたショコラの専門店なんですが、クッキーもおいしいって評判なんですよ。なかなか手に入らないそうです」 そう言ったのは、サブマネージャーだ。和孝も噂は耳にしている。そのショコラ専門店のオーナーは日本人だが、本場フランスで修行したらしい。 「ラッピングもお洒落らしいですね。毎日行列ができているとか」 津守(つもり)が同意した。 毎年、この時季になると必ずこの話題が持ち上がる。 正月、クリスマスなど世間にはイベントと称されるものが存在するが、BM(ブルームーン)も例外ではない。会員からの要望があれば、正月料理でもケーキでもシャンパンでも準備し、イベントムードを盛り上げる手伝いをする。 BMの会員もその同伴者も圧倒的に男性が多いものの、バレンタインデーにスタッフへの心付けという意味でチョコレートを持参する女性客もいる。俗に言う義理チョコであろうと、けっしておざなりではない。BMのスタッフに滅多なものは手渡せないという心理が働くのか、それとも自尊心か、競争心か。彼女たちの心情は計り知れないが、いずれも高価で立派な代物だ。 こちらもいただきっぱなしというわけにはいかない。世間にはバレンタインデーに対して、ホワイトデーという日がちゃんと用意されているのだから。 下手なものは返せないので、三月になると給湯室はその話題で持ちきりだった。 「今年はその店にしようか」 和孝の一言で、ようやく店が決まる。買い出しは若いスタッフの仕事だ。あらかじめ個数分の予約を入れるが、店によっては列に並ばなければならない。 「じゃあ、あとのことはよろしく頼みます」 コーヒーカップを置き、その場で解散する。和孝は津守とともに給湯室をあとにした。 「なかなか大変だ」 津守がこぼす。BMに勤めてまもない津守はホワイトデー初体験だ。BMも客商売である以上、避けられないイベントだった。 「まあね。それも仕事のうちだから」 肩を並べて裏口へ向かうその間、いつものように津守と話をしながら、和孝は先月の一件を思い出していた。 久遠(くどう)のマンションを訪ねた際、リビングのテーブルに堆(うずたか)く積まれた華やかな贈り物の数々を和孝は目にした。 チョコレートと思われる色鮮やかなリボンのかけられた四角やハート形の箱以外にも、いったいなにが入っているのか見当もつかないほど大きな箱もあった。 クラブのホステスか、もしくはその筋関係の女性からか、中にはカードが添えられた「本命チョコ」らしきものもあり、そのどれも包装は解かれていなかったが、つい皮肉を口にせずにはいられなかった。 ――モテモテで羨(うらや)ましいな。 だが、久遠の返答にはむっとした。 ――欲しいなら持って帰っていいぞ。 他人のもらったプレゼントを、やると言われて喜んで持ち帰る人間がどこの世界にいるだろうか。少なくとも和孝はそれを喜ぶ人間ではない。 しかも、久遠と和孝は世に言う恋人関係にあるのだ。 ――いらねえよ。 即座に拒絶した。 ――BMのマネージャーは大量にもらうって? すると、鼻につく一言が返ってきた。冗談じゃないと、和孝は口中で舌打ちをした。 顔には出さずプレゼントの山に手を伸ばす。無言でひとつを拾い上げ、リボンと包装を解いていく。箱の中に入っていたのは、金のネクタイピンだった。改めて箱を見ると、誰でも知っているブランド名が記されている。チョコも同梱されているが、むしろそちらのほうが添え物だろう。 添え物をつまみ、口に放り込む。甘さと苦さのバランスが絶妙で、高級チョコだけのことはあると咀嚼(そしゃく)しながらいまいましく思う。 ――あんたも食べたら? せっかくもらったんだろ? 和孝にしてみれば、皮肉の続きのつもりだった。が、それも通じなかった。 ――これでいい。 久遠は、和孝のシャツの胸元を掴んだ。かと思えばぐいと引き、舌を口中へと侵入させてきた。 口の中で溶けていたチョコレートを、久遠の舌先がさらっていく。 ――甘いな。 感想は一言だったが、和孝を動揺させるには十分だった。結局、和孝は反撃どころか文句ひとつまともに返せなかったのだ。 「柚木(ゆぎ)さんは?」 津守に水を向けられ、先日の出来事を反芻する行為に意識を奪われていた和孝は、はたと我に返った。うっかり、その後ベッドに直行したところまで思い出しそうになっていたので、気まずさから目を瞬かせる。 「……ごめん。聞いてなかった」 和孝が謝罪すると、津守は肩をすくめる。その様子が、まるでしようがないとでも呆れているように見え、なおも決まりの悪さを味わった。 「イベントに凝(こ)るタイプかどうかって」 「イベント、か」 咳払いひとつで頭の中の久遠を追い出し、津守の問いかけに思考を向けた。 「俺はプライベートじゃ凝らない。というか、気にしたこともないな」 それは、事実だ。 仕事上、他人の動向ばかりを気にしているので、プライベートでの和孝自身はそういう面ではかなり適当だった。いや、もともとの性格のせいかもしれない。過去には、短い間とはいえ彼女らしき相手もいたにはいたが、和孝のそういう部分が振られる原因のひとつだった。 久遠との関係に限っていえば、イベントもなにもない、というのが本音だ。クリスマスや誕生日をともに祝う場面を想像しただけで薄ら寒くなる。 「津守さんは?」 津守なら抜け目なさそうだという和孝の予測は当たっていた。 「俺はわりと好きなほうだな」 津守はそう答えると、ただでさえ女性が放っておかないだろう端整な面差しに微苦笑を浮かべた。 「どうも世話焼きな性分らしくて、なにもかもセッティングしてしまうせいでうざがられる」 ため息混じりの告白に、津守らしいと和孝は吹き出した。気遣いが行き過ぎてしまうのだ。なまじ器用でなんでもできるので、それを鬱陶(うっとう)しいと感じる人間がいたとしても不思議ではなかった。 「どっちもどっちか」 和孝はそう言い、先に裏口のドアから外へ出る。津守と別れ、車に乗り込むと帰路についた。ひとりの車中で、どっちもどっちと言えばまさに自分たちだと、和孝は唇をへの字に歪めた。 一緒に祝うかどうかは別として、クリスマスや正月どころか、互いの誕生日ですら知らん顔だ。久遠に至っては、和孝の誕生日がいつなのか把握すらしていないだろう。 もっとも久遠に「おめでとう」とケーキでも用意された日には、なにか裏でもあるのかと心配になるので、このままのほうがいいのかもしれない。 赤信号でいったん停車した和孝は、前方のコンビニの看板に目を留める。信号が青に変わった瞬間に、心を決めていた。 ウィンカーを出すと、コンビニの駐車場に滑り込んだ。 目的は、ホワイトデーのクッキーだ。店内にはコーナーがあり、色とりどりのリボンが並んでいた。 青い包装紙に金色のリボンがかけられたものを手に取る。そのままレジに持っていき、千五十円支払った。 コンビニの袋に入れてもらい、車へ戻る。向かうのは久遠のマンションだ。 ちらりと助手席のクッキーに目をやると、口許が緩んでくる。これを差し出したとき久遠がどんな反応をするか、思い浮かべれば可笑しくてたまらない。 ひとがもらったチョコを食べてしまった、そのお返しだと言ってやろう。さしもの久遠もばつの悪い思いをするはずだ。 欲しいなら持って帰っていいなんて言葉がいかにデリカシーに欠けるか、思い知らせてやるのが目的だった。 久遠のマンションまで上機嫌で車を走らせる。エレベーターで最上階に上がる間に真顔をつくり、門扉(もんぴ)をくぐって玄関のドアから入った。 久遠はリビングダイニングでソファに腰かけ、煙草を手に朝刊を読んでいた。ちらりと視線を投げかけてきたが、言葉はない。いつものことなので気にせずまっすぐキッチンに向かうと、ふたり分のコーヒーを淹れた。 カップをひとつ久遠の前に置き、自分の分に口をつける。陽光の射し込む坪庭を眺め、人心地ついた和孝は、コーヒーの香りに混じる久遠のマルボロの匂いを嗅ぎながら、持参したクッキーをいつ手渡そうかと思案していた。 コーヒーを一口飲んだ久遠が、朝刊を置く。そのタイミングを逃さず、和孝はわざわざ久遠の隣に移動した後、コンビニの袋からクッキーを取り出しテーブルにのせた。 久遠が視線で問うてくる。 どんなリアクションが返ってくるか、期待のために頬がぴくぴくして真顔を保つのが大変だった。 「もうすぐホワイトデーだろ? この前、久遠さんのチョコを食っちまったから、そのお返し」 久遠さんの、という部分を強調する。怪訝な顔をするか、それともきまりの悪さに眉をひそめるか。 久遠を熟視した和孝だが、予想はどちらも外れた。 「ホワイトデーか」 眉ひとつ動かさずに久遠はそう呟くと、和孝の目の前でリボンと包装を解いた。蓋(ふた)を開け、クッキーを口に放り込む。 あまりの反応の薄さに、「ハッピーホワイトデー!」くらいの一言は必要だったかと考え、まさにそう言ってやるつもりで口を開いた和孝だったが……。 実行できなかった。久遠に額を小突かれたためだ。 不意打ちに、背中からソファに倒れる。すぐさま体勢を立て直そうとしたが、体重をかけられては身動きできない。 「せっかくだから、俺も返そう」 「……は?」 どういう意味だ。なにを返すって? 問う必要はなかった。 「ゆっくり味わえ」 久遠の唇の端が吊り上がる。その表情を間近にしてようやく久遠の意図を悟った和孝は、頬を引(ひ)き攣(つ)らせた。目論見が外れたばかりか、結局、今日も久遠のペースだ。 どうも納得がいかない。近づく唇を避けて睨みつけた。 「それは、あんたのほうだろ」 むしろこっちの台詞(せりふ)だ。反論した和孝に、久遠は逆らわなかった。 「そうか。なら、味わわせろ」 「…………」 ふたたび触れてきた唇に、顔をしかめる。そもそも自分がなんのためにコンビニに寄ってクッキーを買ったのか、その目的すら思い出せなくなっていた。思い出すのも面倒だ。どうせやることはひとつなのだから。 「だったら残すなよ」 せめてもとそう告げ、和孝は久遠の背中に両手を回すと自分から口づけを深くする。 煙草とクッキーの混じった味は、そう悪いものではなかった。  甘い言葉は決して口にしない久遠。でも、態度はその反対で!? 本編VIPシリーズもぜひ御一読ください! 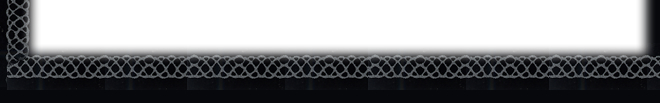
|